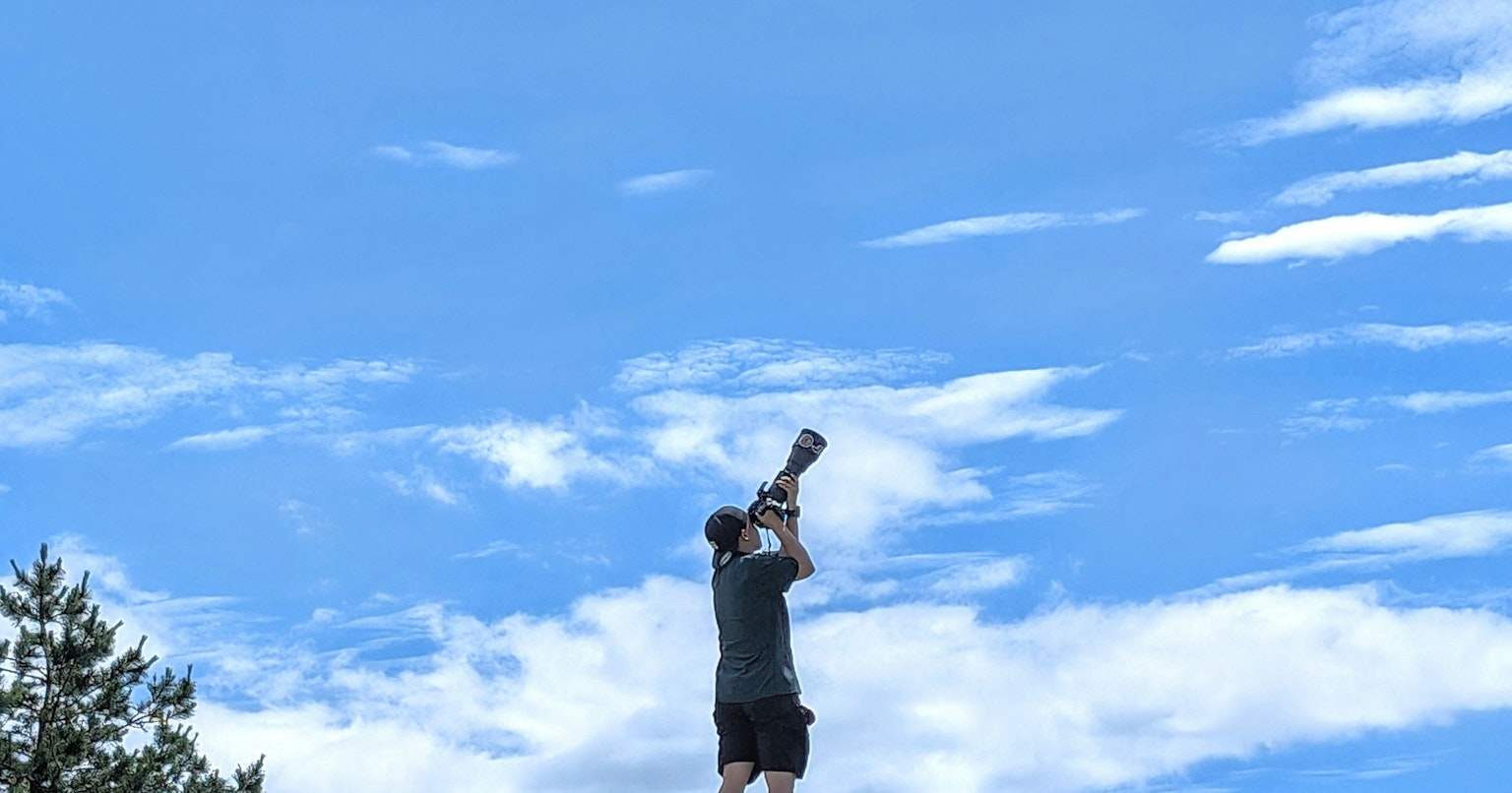
Cover photo by AYUMOON
오늘날 AI는 이미지에 포함된 건물, 자연, 조명과 같은 시각적 단서를 통해 촬영된 장소를 높은 정확도로 추정할 수 있습니다. GPS 데이터나 EXIF 정보가 없어도, 건축 양식, 식생 패턴, 지역 특유의 도로 표지판까지도 위치를 특정하는 데 활용될 수 있습니다.
Google Lens, Yandex Images, OpenAI의 CLIP 기반 모델 등 다양한 도구가 80~90%의 정확도로 위치 추정을 실현하고 있으며, 관광업, 재난 조사, 고고학 등 다양한 분야에서 활용이 확대되고 있습니다. 하지만 일상적인 이미지 공유의 안전성에 대한 의문도 제기되고 있습니다.
AI 활용이 촬영 장소 탐색을 바꾸다
AI 도구를 활용해 오랜 기간 촬영해 온 지역에서 놓쳤던 촬영 장소를 여러 곳 발견한 사례도 있습니다. 구체적인 지명 제안을 통해 창작의 폭이 넓어지고, 기존 로케이션 헌팅에 소요되던 시간도 크게 줄일 수 있었다고 합니다. 이처럼 AI는 편리한 도구를 넘어 창의적인 활동을 지원하는 존재로 주목받고 있습니다.

Photo by fuji
반면, 도구의 정확도가 높아지면서 타인이 게시한 일상 풍경 사진에서 무의식적으로 개인의 행동 반경이 특정될 위험도 부각되고 있습니다.
프라이버시 침해 가능성과 그 위험
SNS에 일상 사진을 게시하는 것이 예상치 못한 위치 특정의 출발점이 되는 시대입니다. AI는 사진에 담긴 배경을 통해 자택, 통근 경로, 학교 등을 추정할 가능성이 있으며, 사이버 범죄나 스토킹의 온상이 될 우려도 있습니다.
기존에 효과적이었던 Exif 데이터 삭제만으로는 더 이상 충분하지 않으며, AI의 이미지 분석 '눈'을 의식한 새로운 위험 관리가 요구됩니다. 스탠포드 대학 학생들이 개발한 PIGEON은 자연 풍경의 위치를 35마일 이내의 정확도로 특정할 수 있습니다.
‘AI 시대’에 우리가 할 수 있는 프라이버시 대책
가장 중요한 것은 스마트폰이나 카메라의 '위치 기록'을 비활성화하는 것입니다. 또한, 공개 대상을 제한하고 신뢰할 수 있는 플랫폼에서만 사진을 공유하는 것이 권장됩니다.

Photo by Yuya
사진 배경에 보이는 간판, 통학로, 건물 외관 등이 '단서'가 되지 않도록 게시 전에 검토하는 습관도 중요합니다. AI가 '파악하는' 능력을 갖춘 지금, 각자가 위험을 이해하고 스스로를 보호하려는 자세가 필요할지도 모릅니다.



